育児・介護休業法の改正により、令和4年10月に「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が創設されました。さらに令和5年10月からは、男性の育児休業取得を促進する目的で制度が改正され、育児休業の分割取得回数も拡大されるなど、制度はより柔軟で利用しやすいものへと進化しています。
当社においても、こうした変化を積極的に受け止め、育児休業を希望する従業員が取得できる環境づくりを進めております。誰もが仕事と家庭を両立し、それぞれの幸せを実現できるよう、今後も働き方改革を推進してまいります。
令和7年4月1日
株式会社学研メディカルサポート
代表取締役社長 清水 修
社員が仕事と子育てを両立することができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、 全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しております。
1.計画期間 令和6年10月1日~令和8年9月30日までの2年間
2.取組内容・実施計画
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、 次のように女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しております。
1.計画期間
2.取組内容・実施計画
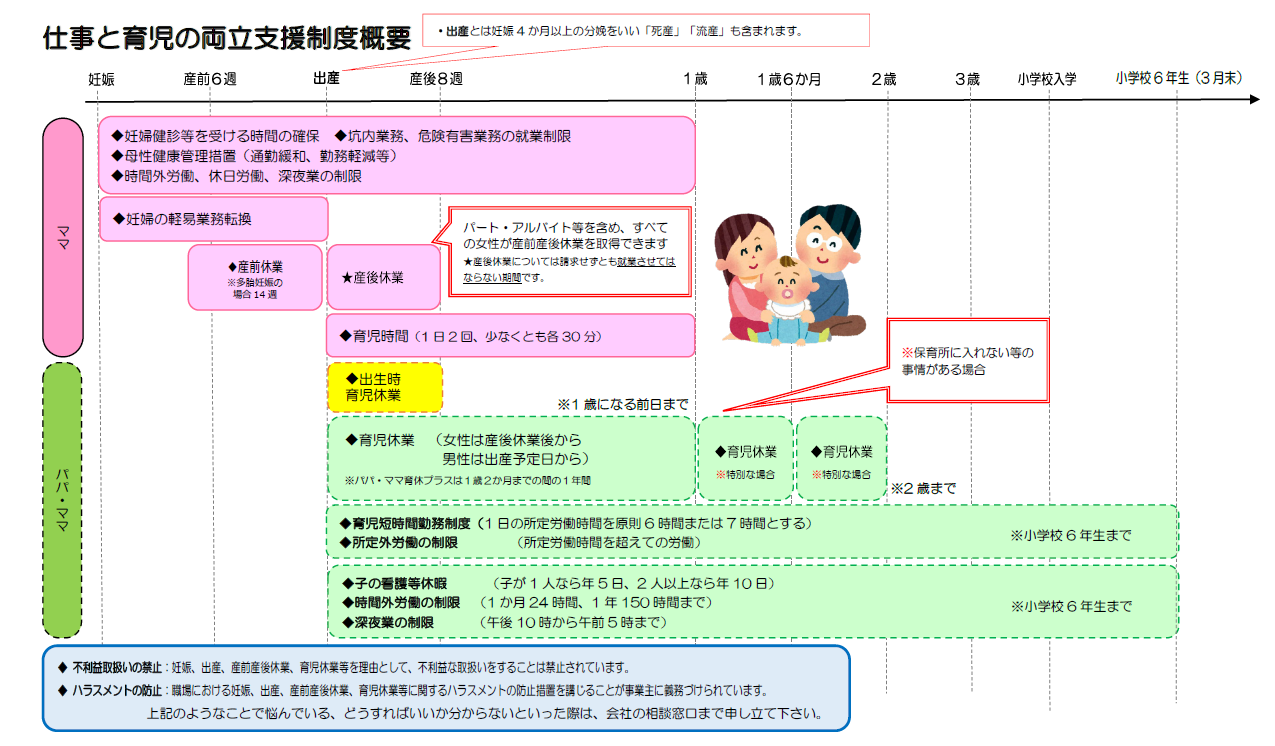
所 属 : 制作部 映像制作課
氏 名 : S.Sさん
取得期間: 子の出生2か月後から5週間
~当社、1人目の男性育児休業取得者~
取得したいと思ったきっかけ
妻が早期の復職を考えていたこともあり、夫婦どちらかが忙しかったり、休養が必要な場合に、もう一人が無理なく家事育児を交代できるよう、家事育児スキルのトレーニング期間を確保するために、育児休業を希望しました。
配偶者の反応
妊娠判明時より父親の育休についても話し合っていたので取得は想定内でしたが、必要なタイミングはどこか、その期間に何をするかなどの目測を夫婦で考えることで得られる安心感はあったようでした。
上司・同僚の反応
育休取得期間が自部署の最繁忙期であったにもかかわらず、まったくそのことは関係ないかのように応諾してくれ、業務調整や引き継ぎを積極的に行ってくれたので、本当にありがたく、安心して取得できました。
自部署の同僚に早めに取得期間を伝え、その間の業務に関する割り振りや案件ごとの引き継ぎ、自分だけが出席していた会議に同僚や後輩に出席してもらうような調整、溜め込んでいた資料の整理なども行いました。
取得にあたって準備したこと(家庭・子育て面)
妻子が里帰りから自宅に戻るタイミングでの育休取得だったので、家の中の掃除や子どものいる生活にあわせた家具の配置替えなどの準備を行いました。
育児休業中どう過ごしたか
洗濯、料理、ミルク、おむつ、子どものうつ伏せ練習や散歩、寝かしつけ、夜泣き対応を行う毎日でした。週1回は皆で車でおでかけする日、週に半日程度は夫婦それぞれ一人で外出して息抜きする時間なども作りました。
復帰後の働き方と育児について
働き方は大きくは変えない予定でいますが、子どもの急な発熱や不測の事態にも対応できるよう、業務をより周囲と共有していきたいです。自分だけでなく、皆が互いに助け合える仕事の進め方ができればと考えています。
育児休業を取得した感想
子どもがとにかくかわいくて、楽しい思い出も作れました。でもそれよりも、泣き止まない子どもを抱えて朝を迎える辛さ、一日が洗い物だけで終わる虚無感みたいな大変さこそが、貴重な時間と感じさせることにつながったと今は思っています。
これから育児休業を取得する男性職員へのメッセージ
社会人としてふるまい対応する毎日から、社会人としてのスキルなんてなんの意味もなさない存在と向き合う毎日になるので、戸惑うことも多いです。でもそれは人生をひとつ豊かにする日々だと思います。楽しんでください!
上司からのメッセージ
当社で初めての男性の育休取得でしたが、本人からの早期の取得相談が体制整備につながりました。業務整理と後輩への権限委譲は、復帰後の本人のステップアップに直結したと感じます。今では男性の育休取得はもちろん、男性間での育児談義も活発になり、会社全体に、業務に集中する力とプライベートを充実させる活気が醸成されました。
所 属 : 営業部 営業促進課
氏 名 : T.Tさん
取得期間: 子の出生直後から1か月間
~当社、5人目の男性育児休業取得者~
取得したいと思ったきっかけ
妻には持病もあり、産後は回復に専念してほしかったこと。そして、多様性といわれる社会でもあり顧客は女性が多く子育てに理解があったことです。
加えて、前職は外資で男性育休が長く定着しており、現職の良い職場環境をさらに良くしたいと思いました。
配偶者の反応
とても喜んでもらえました。親族友人も会社のイメージがより良くなったようでした。私が居なかった場合、妻が産後うつを発症するリスクがあったと感じたので取得できてよかったです。そして、育児経験したことで妻からさらに信頼を得られ、私の仕事への理解が深まりました。
上司・同僚の反応
みなさんおめでとうといってくださり、オープンな形で接してくれたため、相談しやすかったです。当たり前のことのように手続きを進めてくれたこともよかったです。
取得にあたって準備したこと(仕事面)
育休取得中にある顧客対応の方法の引継ぎを準備しつつ、仕事をしながら、この仕事は他の人でもできないかと考えました。そして、次の育休の人にも再現性があるように業務調整を考えました。
取得にあたって準備したこと(家庭・子育て面)
周りの理解があって、取得できたという説明をしました。そして、両家に1か月間は取得できると伝え、その後はサポートが必要かもしれないことも伝えました。
育児休業中どう過ごしたか
家事はすべて自分で妻には回復に専念してもらいました。
育児は交代制で夜から朝までのミルクやおむつを担当し、それに伴いミルクの量、寝かしつけ、おむつなど育児について勉強もしました。
他にも、行政手続きを行ったり、妻へのメンタルケアを行ったりしていました。
復帰後の働き方と育児について
働きながら育児や家事において自分でできることと、育休中の妻にしかできないことを整理しました。そして、妻が職場復帰を予定していたので、また話し合う必要があると感じていました。
育児休業を取得した感想
仕事をしていたほうが楽な時もありましたが、自分が育児休業を実際に取得したことで、妻から日々報告を受けた際、上辺ではなく「大変だったね」といえるようになりました。
そしてなによりも楽しかったことと、ミルク、沐浴、おむつ、寝かしつけなど基本的なことが覚えられました。
これから育児休業を取得する男性職員へのメッセージ
妻のためという側面も大きいです。長い目で見て、もし妻の回復が遅れた場合や、信頼関係が得られない場合、後々の自分の仕事にも影響します。総合的に考えて楽しくいい経験になるので取得をお勧めします。
【制度に関するお問合せ、相談窓口】
管理部 人事課
電話 :03-6431-1249
Email:gmeds-jinji@gakken.co.jp